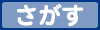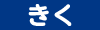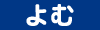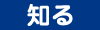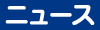死後の世界がいくらないと理屈では考えていても、頭から否定することが難しいのだ。
[ 宮城一春(編集者・ライター) / 2013.11 ]

2005年2月発行
崎原恒新 著
むぎ社 刊
B6判/352ページ
1,800円(税抜)
出版社のホームページへ
琉球の死後の世界
崎原恒新 著
今年に入って、近親者やお世話になった方の告別が多くなった。特に今月(8月)は、連続して4件の告別式へ行った(ただ、そのうちの一つは、親戚で、私が墓開け当番だったので告別式には参列していないが)。
20代から30代前半にかけて、結婚式への参加が多かった。沖縄では誰でもそうだと思うが、結婚式難民というか、お祝いで懐が寒くなるほど。幸か不幸か、私はあまり友人がいないので、頻繁に参加したわけではないが、知り合いの中には、毎週末結婚式へお呼ばれされている者もいたほどだ。
それからしばらくは、出産のお祝いが続いた。
それが、30代後半から告別式へ出ることが多くなった。いろいろな義理もあるので、毎日の新聞チェックは欠かせない。
それだけ死が身近になってきたということだろう。
私自身、人間は、死んだら無の存在となると考えているが、臨終から通夜、告別式、納棺と一連の流れを見ると、遺族や関係者の悲しみ(もちろん、私自身も含めて)は、何かしらこの世に残っていくものだろうと思うようになった。
その方が記憶に残っている限り、死というものは、私たちの身近にあるのだと思うのだ。
そこで本書。「はじめに」の文章の中で、著者である崎原氏は、死や死後の世界について、こう述べている。少し長くなるが、引用してみたいと思う。
琉球でもそうであるが、人々は死後の世界の存在も認め、また人間以外の妖怪の存在も、神々の存在も認めてきた。さらに、生物的な死霊・妖怪変化だけでなく、生物以外の怪異の存在も認めてきたといえる。
もちろんいつの時代でもそうであるが、死後の社会や異界に対する考え方は、その時代と社会情況によって一つの流れを形成する。しかしまた、同時に地域差や個人、個人による認識の相違も当然あったはずである。死後の社会の存在を否定することが極めて困難であったことも事実であったと思われる。
たとえば家族や親族の死に直面したとき、その意味は単なる骸として処理することはしないし、一六日祭・清明祭・年期法要にも参列し、供養を行う。知人、友人の死去に際しても、死後の世界が無いとして参加しないことはない。単なる義理や形式だけではすまない側面を持っているといえる。
死後の世界を否定する者でも、あれはいったい何であったのだろうと回顧する体験を持つ者も少なくないと考える。私もこのような体験をしたことがある。
そうなのだ。死後の世界がいくらないと理屈では考えていても、頭から否定することが難しいのだ。告別式や周忌法要、一六日祭や清明祭、盆、彼岸など、あの世の行事を行っているウチナーンチュにとって、死後の世界を簡単に否定することは、人情的に困難なことなのだと思う。
本書は、「琉球の異界」の概況から始まって、「死のまえぶれ」「生き返った話」「幽霊のはなし」「火の玉」「動物の怪・植物の怪」「その他の妖怪たち」「道具の怪」「まよけとまじない」と九つの章からなっている。
何と、動物や植物にも怪異が見られるのだ。ああ、道具にもかあ。といった感じで、様々な怪異が語られていく。
それが、崎原氏の調査に基づいているだけに、それぞれの地域の人びとの生の声が聞こえてくるような感じがしてしまうほど。
所変われば品変わると、よくいわれることだが、この狭い沖縄ではあるが、地域によって本当に違いがあるんだということが理解できた。
それくらい、死というものが近くにあったのだろうし、自然に近かったのだろう。また、日常生活の中で使う道具類も大事に、大切に使っていただろうということが分かるのである。
現代の私たちには計り知れないほど、死や死後の世界が身近であり、切実感をもって感じられただろう、かつての沖縄。
沖縄にはまだまだ私たちの知らない世界があるということを、本書は教えてくれたし、知らなければならないと警告してくれているような気もした。
そして、死後の世界とうまく付き合ってきた昔人たちから、こうして死後の世界とは付き合っていくんだよという、私たちへの優しいヒントを与えてくれているような気がする。