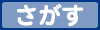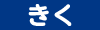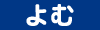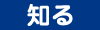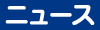ビックリすると同時に、是非見てみたい、乗ってみたいと夢想する乗物となった。
[ 宮城一春(編集者・ライター) / 2014.02 ]
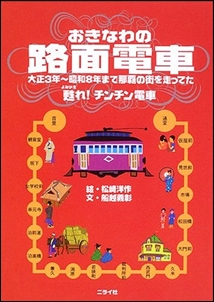
2006年07月発行
絵:松崎洋作
文:船越義彰
ニライ社刊
絵本(B5判)/46ページ
1,500円(税抜)
出版社のホームページへ
おきなわの路面電車 甦れ!チンチン電車
―大正3年~昭和8年まで那覇の街を走ってた
絵:松崎洋作/文:船越義彰
沖縄にもあった、こんな風景。
モノレールが那覇の街を走り始めて風景が変わった。
私の住む部屋からも、町並みを縫うように走っていくモノレールの姿を見ることができる。まるでオモチャのようなモノレールだが、近隣の住民にとっては、有り難く大事な乗物にちがいない。
私も時折利用するが、学生や通勤客、観光客が乗っている。那覇の新しい風景や古い町並みを走るとき、近代的なモノレールと私の住み慣れた那覇の街が渾然一体となって目の前に現れてくる。
私の生まれ育った町を通るモノレール。
そのモノレールを見ていると、そこに、ある既視感を抱いてしまう。
幼いころの私、小学校で遊んでいる私、中学校の部活で汗を流している私、ぶらぶらとのんびりと高校への道を歩いている私。それらの上空を飛び、私の成長していく姿を見ているような錯覚に陥ってしまうのである。
公共の交通機関は、ある記憶をもって語られ、そしてさまざまな人たちの生活を彩っているに違いない。
そこで本書。
タイトルからもわかるように、那覇市内を電車が走っていた時代の話である。
しかし、沖縄を、それも那覇を路面電車が走っていたなんて……。
それも、大正8年から昭和8年までの20年間だけだなんて……。
それも、6.9キロメートルの営業距離しかなかっただなんて……。
軽便鉄道だと思っていた泊高橋を走っているのが、路面電車だったなんて……。
そんな……が、いくつもつくようなことが、表紙から伝わってくる。
これまで軽便鉄道の存在しか知らなかった私にとって、この路面電車の存在はビックリすると同時に、是非見てみたい、乗ってみたいと夢想する乗物となった。
本書の特徴は、何といっても、見開きで展開されていく路面電車20の駅周辺の絵。そして、エッセイとしても読めるし、歴史の一こまの解説としても読める船越義彰氏の文章。
さらに、今となっては、見ることも、面影を探すこともできない当時の風景を、松崎洋作氏は見事なまでに再現し、船越氏は、文章で当時の駅周辺の光景を切りとっている。
また、ページの右端に掲載されている古い写真が、二人の描く路面電車の駅を補完してくれる。三者が自分を主張し合いながら融和している感じなのだ。
そこには、20の駅の特徴を捉えている。住んでいる人々が造り上げているもの、地理的条件が造り上げているもの、中心となる建造物が造り上げているもの、いくつもの駅がこの本の中に満ちあふれている。
失ってしまったものへの憧憬と、切りとられたものに対する痛みがある。
内容まで深く書くことができないのが残念だが、とにかく、松崎氏と船越氏の絵と文が秀逸な本なのだ。
特に、船越氏の文からは、かつて読んだ『沖縄物語』(古波蔵保好著)の、郷愁溢るる長閑なる沖縄の風景、王府時代のスインチュの姿や、『なはわらべ行状記』(船越義彰著 沖縄タイムス社)にみる幼い子どもの視線から見た那覇の街や、当時の大人の姿を思い出してしまった。
また、那覇の民俗地図を立体的に見ることができるような気がした。
48ページの本だが、この本からは、たくさんの情報とたくさんの思い、そしてたくさんの連想が生まれてくる。
この本の中を走っている路面電車は、私が生まれた場所と現在住んでいるところを結んで走っている。もし、今、路面電車がこの線路を走っていたなら、私はこの路面電車とともに成長していったことだろう。
本書の中で展開されている那覇の街は決して私の知っている那覇ではない。だからこそ、本書の絵と文、写真の中で、自分なりの那覇の街を想像して遊んでみることができるのかもしれない。
絵の中に、溶け込んでしまいたい、一度でいいから電車に乗ってみたい。そう思わせる絵本である。
いや、本書を読みながら、戦前の長閑な街並みを歩いている私がいた。それは事実である。