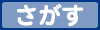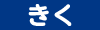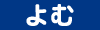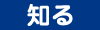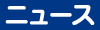1963年の黒島で、自然の猛威に必死で向き合い祈るよりすべもない人々の背後に「神々の残映」を見いだした。
[ 大森一也(写真家・編集者) / 2014.02 ]

2006年9月発行
吉田元 著
冬青社 刊
264×258×15mm/96ページ
3,000円(税抜)
出版社のホームページへ
神々の残映 沖縄・八重山・1963
吉田元 著
表紙には、男の表情のアップ。
焦げたように真っ黒に日焼けした顔の皮膚。目元に刻まれた深い皺。風にあおられないように農作業用のものよりはツバの広がりの少ないクバ笠。いずれも吹きつける潮風と、照りつける強烈な太陽光に逃げ場もないまま長年さらされ生きてきた海人の証だ。
生きざまや個性を十分に語る人物像で写真集の表紙を飾ることは、別段、珍しいことではない。
だがよく見れば、男は眉間に深々と皺を寄せ、口元は何か、うめきにも似た言葉がこれから発せられるかのように、半開きになっている。そして、視線は不安げに遠くの空に向かってのびている。本文の同じ写真には「薄明りの出漁」とキャプションがあるので、おそらく、今日の天候、雲行きを心配してのことだろうか?
それにしても表紙を飾る写真に、なぜ、このようなどこか不安げで心配そうな表情のものを使ったのだろう。男は、いったい何を見つめているのだろう。
2006年に発刊された写真集『神々の残映』は、同時に発刊された『北回帰線の北』とともに2005年に他界した吉田元の遺作である。
1963年のテレビドキュメンタリーの撮影に同行し、7月から11月までの70日間、八重山諸島に滞在しながら撮影したモノクロの写真群と、散文詩のように情感あふれる文章からなる作品集だ。
同書に収められた写真作品は49点で、「牛飼いの夏」「海人」「結願祭」「ミーニシ(新北風)」「日没」の五つに大別されている。
その多くは黒島で撮影されたもので、浜辺の茅葺き家、野良仕事から帰る親を待つ子ども、焚き木ひろい、貝や海草を採ってリーフから戻る女性、祭りで踊る姿など、日本復帰前の沖縄の離島における人々の素朴な暮らしぶりが、愛情あふれる眼差しで、美しき物悲しさを湛えながら切り取られている。
――写し撮られたのは素朴な民俗でありながら画面にあふれる「美しさ」と「物悲しさ」。
それが、この作品に類書とは別格の気品を与え、観るものの心を吸い寄せるのだが、それらはなぜ、かくも際立ち、しかも響きあうように存在するのだろう。
作者が訪れた1963年の八重山諸島は、未曾有の大干ばつに襲われ、飲み水も底をつき、牛など家畜の食べる草は枯れ、人々はうらめしく空を仰ぎながら、雨をもたらす台風に期待を込めた。
しかし、台風も風ばかりの「ピーカジ(火風)台風」で、塩害により植物はますます枯れる一方であった。黒島のように、隆起サンゴ礁の平べったく表土の薄い島では、天水やわずかな井戸水に頼るのみで、唯一の換金作物であるサトウキビが枯れ、牛が餓死すれば、人々の多くは暮らしていけなくなる。
9月には 《800人の島びとのうち、すでに17家族100人近い者が石垣島や沖縄本島に新しい暮らしの活路を求め島を出た》という。
当時のこうした状況からすれば、作品が辛さや悲しみ、怒りなどを強調する激しいドキュメントになっても不思議はないところだが、描写された映像は、まるで一編の抒情詩のように静かに心に沁みこんでくる。
あとがきの中で作者は次のように述べる。
一粒の実りもない年でも、いや、最悪の年なるがゆえに、かえって、いや増しに神に豊作を感謝し、決して豊かではない島を〈げにや豊かぬ〉と歌って神に奉り、とりすがる心は、いっそう激しく切なる焔となって燃え盛っていたのではなかったか。
1963年の黒島の結願祭についても
人間は、たちまち神と人との垣根を越えて、並みの人間の計り知れぬ世界を浮遊しているようであった。かれら男女は神の世界を漂う者だけの幸せに満ちていた。
という感想を記している。
そして1980年代、東京の国立劇場で行われた民俗芸能の催しで、作者は八重山から来た演者たちの中に黒島で親しくなった数人の男女の姿を認め、彼らの踊りを観賞するのだが、
昔、島のワン(御嶽)で神に奉じ、神人とともに楽しんだ、その同じ人間の演技とは到底思えなかった。
空疎きわまるものに思えた。
という。
すぐ隣島まで迫ってきた観光と公共投資の銭金囃しの大太鼓を耳鳴りに、神ではなく(とうに居ない)、人に聞かせ見せるための芸能として流派や保存会や研究会や社中から選び抜かれた代表という重荷を荷い、壮絶にして悲壮をきわめた生き残り道を血みどろになって探り、誇示し、競い合っていたのであろう。
と分析し悲嘆する。
ここに至り、全編を通じた「美しき物悲しさ」の出所がなんとなく分かってきたような気がする。それは、干ばつという事象そのものに由来するのではなく、むしろ物質的な豊かさや生活の便利さとひきかえに神と乖離していく現代の人々の姿、それこそが作者の感じる物悲しさの源泉であり、この離島にすら早晩、「神なき世界」が訪れることを予感した者の悲しみではなかったか。
だからこそ作者は、1963年の黒島で、自然の猛威に必死で向き合い祈るよりすべもない人々の背後に「神々の残映」を見いだし、それがことさら愛しく、また美しく輝いて見えたのではないだろうか。
改めて表紙の海人の写真を見ると、不安げな遠い視線の先は、去っていく神々の後ろ姿を追っているのではないかという気さえしてくる。
そして、扉を開けた最初の写真「砂糖黍をかじる少女」の画面いっぱいに広がる笑顔を見るたび、「神々の光」が島々のどこかに残されていることを切に願い、祈るような気持ちで光と影の交錯するこの美しい作品集のページを、繰り返し、繰り返し、めくってしまうのだ。