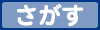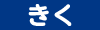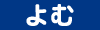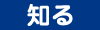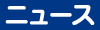どん底だと思う瞬間でも自分を変えていくことが可能であり、目標を描いていれば、そこへ到達できる自分がいる。
[ 宮城一春(編集者・ライター) / 2014.06 ]
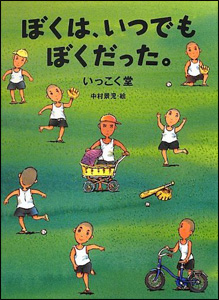
2012年9月発行
いっこく堂 著
イラスト:中村景児
くもん出版 刊
A5判/141ページ
1,200円(税抜)
出版社のホームページへ
ぼくは、いつでもぼくだった。
いっこく堂 著
いまや日本を代表するエンターテイナーと称しても、過言ではないほどの輝きをもつ腹話術師 いっこく堂。
本書は、そのいっこく堂の半生記である。神奈川で生を享けながらも、沖縄出身であると誇りをもって言い続けているのは、「自分を育ててくれたのは沖縄である、と確信している」から。
それでは、家族とともに帰郷したいっこく少年を待ち受けていたものは、なんだったのか。 そこには、米軍施政権下の沖縄の姿があり、その中で必死に生き抜くウチナーンチュたちの姿があった。
もちろん、いっこくの父母も生活のために必死に頑張っていく。その姿はいっこくの目には、どのように映ったのだろうか。
本書は、沖縄の現代史を踏まえ、彼が育った日本復帰前後の基地の街・コザの様子が子どもの視線で描かれている。
そこには、子どもたちならではの、復帰に対する感想なども散りばめられている。多分、情報が氾濫している現在の子どもたちには理解できないだろうなという記述もある。
でも、そこが当時の子どもたちらしいし、今現在、テレビでみるいっこく堂の姿とダブって見えるところもあって共感できることだろう。
また、いっこくが体験した2回にわたるいじめの記憶も正直に綴っている。
最初は、教員の不用意な発言がきっかけ。
2回目は、少年期特有の友人関係がきっかけのいじめ。
いずれも、いじめの陰湿さや不条理さがあり、心を締め付けられるような感覚にとらわれてしまう。
そのときに登場するミュージシャンの佐渡山豊さんが、またカッコいい。
まさしくいっこく少年にとってのヒーローであっただろうし、救世主であったに違いない。
さらには、本書は、現在まで続く沖縄の実態をも描き出している。単なる功者が紡ぐ成功へのありきたりの実用書ではないのだ。
そして読者が一番知りたいであろう、腹話術師への道も描いている。が、いっこく青年の前には、どこまでも苦難の道が待ちかえているように思える。
そこは本書を読んでもらうしかないのだが、人はどんなどん底だと思う瞬間でも自分を変えていくことが可能であり、目標を描いていれば、そこへ到達できる自分がいると書く。
自分が経験したすべてのことが、今の自分をつくったと書き、読者に希望を与える本だ。
本書に描かれている、どの記憶もどの記述も、さまざまな年代の読者(小学生、中学生、高校生、大学生、そしてこれから社会へ羽ばたこうとしている若者まで)の読者でも共感できるだろう。
物事をなしとげること、人の到達できない高みに上っていくことは難しいが、しっかり目標を定め、前向きに生きていれば、挫折も良い肥料になると教えてくれる好著である。
人が人を信じない、もしくは信じられない世界、成功者と敗者の二つしかない世界。いずれも、本当に幸せな世界ではないことを、しみじみと味わわせてくれる本だ。