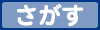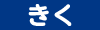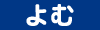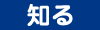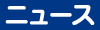「日本でありながらも、日本ではない沖縄」を、岡本太郎の眼差しは厳しくも、柔軟にとらえた。
[ 具志堅梢(「書評ライター養成講座」受講生) / 2014.08 ]
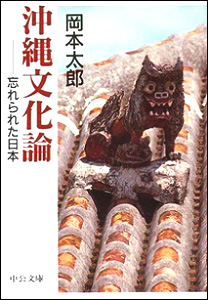
1996年06月発行
岡本太郎 著
中央公論社 刊
文庫判/261ページ
686円(税抜)
出版社のホームページへ
沖縄文化論―忘れられた日本
岡本太郎 著
「芸術は爆発だ」、誰もが知るこの有名な言葉を世に残したアーティスト、岡本太郎。熱い魂と独自の審美眼を築き上げた岡本太郎が、1959(昭和34)年11月に、初めて沖縄を旅したときに書き上げたのが『沖縄文化論-忘れられた日本』だ。
冒頭に書いたように、岡本太郎はとにかく「熱い」のだ。
燃えたぎる太陽、生と死、あふれる情熱、鋭い批判、そして事件。
私自身、どこかアンタッチャブルで危険な男というイメージを抱いていた。ところが、本書から見えてきたのは、岡本太郎の柔軟で優しさにあふれた眼差しだった。
私は1983年生まれ。沖縄戦も、アメリカ占領下にあったオキナワも、本土復帰も知らない。
そんな80年代生まれの人間でも、読みだせば、岡本太郎の視点を通して鮮明に浮かび上がる、1959年の沖縄を「旅」することができた。素朴で純粋な人々の暮らしぶりや風景、戦争で消失した文化財や受け継がれる芸能など、岡本太郎が初めて見た沖縄がとても自然体に綴られているからだ。
その初々しい視点は、時代を知らない私と同じ。
東京から初めて沖縄に降り立った岡本太郎は、王朝文化、戦争、占領、基地など、さまざまな沖縄のまなましい現実を目のあたりにした。
ところが、その厳しい過去と現実を背負うはずの沖縄で、ズレた「沖縄的感覚」を次々と体感していく。
高級クラブハウスのパーティーで、アメリカ軍関係者と地元民らが楽しそうに談笑する。
真夜中、ホテルの従業員が宿泊客に悪気などなく、眠気覚ましに下手なピアノを弾きはじめる。
沖縄にはサービスという意識はないのか。
地元の酒、泡盛を飲まず、舶来品の洋酒で飲み明かす沖縄の友人たち。
それなら僕が泡盛を飲んでやる。
背負った傷やなまなましい現実があるにも関わらず、沖縄の人々はそれを許容し、常に自然体に、穏やかに生きている。
現実と現実のギャップ。
カメラを首に下げ、真っ正面から旅の答えを求めていた岡本太郎だったが、そんな岡本太郎を最も感動させたのは、何も無い久高島の「御嶽」だった。
礼拝所も建っていなければ、神体も偶像も何も無い。森のちょっとした、何もない空地。その何もないということの素晴らしさに私は驚愕した。
答えを真っ正面から求めれば求めるほど、つかむもの・形がないのが沖縄だったのだ。
何もないこと、物を持たないことの素晴らしさ。こういう答えのもあるのかと、よっぽど新鮮だったに違いないと感じた。
芸術に関してだったり、さらには、本土的リズムが「沖縄リズム」によって乱された場合に、時折でる岡本太郎の感情的な部分や、あちら側の意識からこちら側に戻ってきて、思考する岡本太郎の姿が読み取れるのが面白い。
「ズレ」を感じずにはいられない。
日本と沖縄のズレに驚き、怒り、呆れ、笑い、そして受け入れる。「日本でありながらも、日本ではない沖縄」を、岡本太郎の眼差しは厳しくも、柔軟にとらえた。
実は本書は、1960(昭和35)年、中央公論にて1年間に渡り連載された「沖縄文化論」を、1961(昭和36)年に、『忘れられた日本-沖縄文化論』として出版し、毎日出版文化賞を受賞した作品だが、1972(昭和47)年に『沖縄文化論-忘れられた日本』へと改題して再版している。
初版から10年。沖縄の「旅」はまだ終わっていなかったのだろうか。
本書の終わりに、「本土復帰にあたって」という文章を寄せているが、私は、この文章にも強く魅(ひ)かれた。
だから、沖縄の人に強烈に言いたい。沖縄が本土に復帰するなんて、考えるな。本土が沖縄に復帰するのだ、と思うべきである。そのような人間的プライド、文化的自負をもってほしい。
1972年の本土復帰当時の沖縄が抱える問題を鋭く射抜き、これらの課題を解決するのは、沖縄自身なのだと解いた岡本太郎。彼は、今の沖縄を、日本を、どんなふうに見ているのだろう。
1959年の沖縄へ「旅」できる一冊でもあれば、時をかるがると越えて「沖縄」に迫ってくる、岡本太郎の眼差しと対峙する一冊でもある。