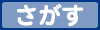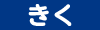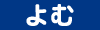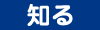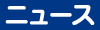あの世とは一方通行ではない、 パラレルワールドのように生者と死者の世界が重なっている。
[ 嘉手川学(オキナワふうどライター) / 2014.09 ]

2014年07月発行
比嘉淳子 著
双葉社 刊
B6判/223ページ
1,400円(税抜)
出版社のホームページへ
グソーからの伝言
比嘉淳子 著
グソーとは沖縄の言葉であの世のこと。あの世といっても本土の人の認識するあの世とは少しニュアンスが違うような気がする。いわゆる本土でいうあの世とは冥界や黄泉の国、彼岸、天国、地獄といった、行ったら行ったきりの一方通行の世界だけど、沖縄の人にとってグソーはちょっと違う世界観なのである。
なんといっても大きな違いは三途の川を渡ったり、あっちの世界に行ったりしないで身近にある世界だということである。沖縄では昔から「グソーやアマダイヌシチャ(雨垂れの下)」といわれており、軒下や樹の下など雨のしずくが落ちる場所にグソーがあるという考えなのである。いわば、生きている人と同じ時空間にグソーがあり、死んだオジーやオバーが身近に感じられる社会というか、我々と同じように死んだ人が生活?している世界がグソーなのかもしれない。早い話が、沖縄の人は死んだ人と共存共栄?しているという感覚を持っているということである。
さて、本書は読むにあたって、沖縄の人の持つこのグソー観を想像して読むと、物語に奥深さが感じられるようになっている。あの世とは一方通行ではない、まるでパラレルワールドのように生者と死者の世界が重なっていると思って読んでもらいたいと思う。
物語の主人公は、都会暮らしに憧れ、関東の大学を出て同郷の男と結婚。子供も生まれ快適な都会暮らしを満喫していたが、夫の実家の都合と望郷の思いから沖縄暮らしに舞い戻る。そこから物語が動きはじめる。舅が準備した高層マンションに住み始めた頃から、主人公やその周辺で異変が起こる。眠れない日々が続き、体調を崩し見えないモノまで見えてしまい、とうとうそれらと会話さえするようになる。そして、見えない者たちを受け入れることで彼女の生きかたが好転していくという話である。
その縦軸には戦争の悲しさや愚かさに腹を立てつつ、子を持つ母親の強さ、生きている人間の不思議な縁を描いている。
見えないものが見えてしまう能力が開花した主人公は、ご主人への愛と思いが強いまま亡くなった美人奥さんの思いと生きている人間の愚かしさに怒りを向けたり、「耳切坊主」というちょっと残酷な沖縄の子守唄と彼女の関係を知る。さらに、幼い頃の自分の能力を思い出した話、自分が住む土地の神様や飼っていたペットと人間とのあさからぬ縁など、随所にグソーと現世の織り成す糸が紡がれる。それによって、全編がタペストリーのように一つの物語りになっている。
本土の死生観やあの世の人に対する考え方でこの本を読むと、成仏できない人が生者に祟る、どちらかといえば怖い話や怪談に入るかもしれない。しかし作者の立ち位置が亡くなった側に立ち、生きている人と同じように愛情を持って接することで、死者に人格が生まれ感情移入ができるようになっている。
沖縄には、成仏できないグソー人がサーダカー(霊力がある人)たちに話を聞いてもらい、その願いを叶えることで成仏できるという考えがあり、これこそがまさに沖縄のグソー観である。
読んでいるうちに、これは物語というよりも、むしろ著者の比嘉淳子さんの私小説ではないかと思えてきた。比嘉さんは子どものころからサーダカーで、見えない人が見えてしまう人だったと思う。グソーにまつわる話を多く知っているからである。
ボクの知り合いのサーダカーの人の話だが、国際通りを歩いていると毬をついている子供がいたので、「こんなところで毬ついたら邪魔になるよ」といったら、その子が「見えるの?」と聞いたという。また、ある日バスに乗っていたら、バスに乗り込んで一人一人の顔を覗き込んでくる青年がいたので、「あ、あっちの人だな。目が合うとめんどくさいなぁ」と思い、自分の番になっても全く無視していたら、そのままバスを降りていったという。でもバスのドアが閉まる瞬間、うっかりその青年と目が合ってしまった。すると青年はしばらく走ってバスを追いかけてきたという。
沖縄のサーダカーは本土の霊能力者と違い、グソーの世界の人を怖がらずに除霊も浄霊もせず、生きていた時と変わらぬ態度で付き合っている。
ナゼならグソーで生きている人?は生前のままだからである。スケベなオジーはスケベなままだし、猫舌のオバーはアチヂャー(熱いお茶)が嫌いだし、シカボー(臆病)オジーはシカボーなままだという。そしてグソーのことを面白おかしく、見えない人に語ってくれる。この本もまさにサーダカーな比嘉さんが面白おかしく語ってくれる、グソーのエピソードが満載の本である。